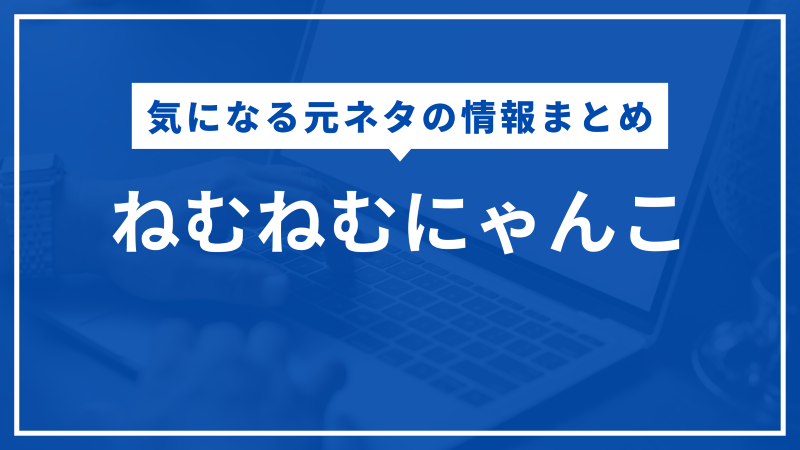「ねむねむにゃんこ」と検索している人は多いですが、元ネタはどこから生まれた言葉なのか、はっきりとした答えが見つからずモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。
「ねむねむにゃんこなのだ」や「ねむねむにゃんこだしん」といったバリエーション、三枝明那さんや加賀美ハヤト(社長)といったVTuberがSNSや配信で使ったことで再注目される場面もありました。
また、PSO2のプレイヤーコミュニティや5ちゃんねるのような掲示板文化、さらにはAAやコピペとしての拡散も確認されています。さらに「と見せかけて」などの派生パターンまで登場し、まるで定義のはっきりしない“ネットスラング”として定着しているのが実態です。
本記事では、ねむねむにゃんこの初出や広がり方、代表的な使用例を具体的に紹介しつつ、元ネタがなぜ曖昧に感じられるのかを整理します。最後にはまとめとして、記事やSNSで触れる際に注意すべきポイントもお伝えします。
ねむねむにゃんこの元ネタに関する基礎知識と重要ポイント
ねむねむにゃんこなのだ
「ねむねむにゃんこなのだ」というフレーズは、「眠い+猫」を可愛らしく擬人化したネット独特の言葉遊びです。
日本語のネットスラングでは「〜なのだ」「〜だにゃん」といった語尾が多用される傾向があり、このフレーズもその系譜に属します。
実際の使われ方としては、夜更かしをして眠気を感じたとき、SNSのタイムラインに「今日はもうねむねむにゃんこなのだ」と投稿したり、日常のかわいい自虐表現として利用されたりします。
検索ユーザーの中には「誰が最初に使ったの?」と気になる方もいますが、ここが難しいポイントです。というのも、この言葉は特定の漫画やアニメが発祥ではなく、複数のネットコミュニティで自然発生的に使われ始め、徐々に拡散していった可能性が高いからです。
起源・初出と2019年前後の広がり
ネット上の痕跡を追うと、2010年代後半にはすでにブログや掲示板で「ねむねむにゃんこ」という表現が見られます。
特に2019年ごろの個人ブログでは「んぅ…ねむねむにゃんこなのだ」といった直接的な使用例が確認でき、そこから「自分が考案したのでは?」と名乗る人も現れています。
ただし、ネットミームの多くがそうであるように、一人の明確な“作者”を断定するのは困難です。むしろ同時期に複数のコミュニティで似たような言葉が使われ、それらが相互に影響を与えながら広まっていったと考えるのが妥当でしょう。
PSO2界隈・AA・コピペ文化との関わり
特に面白いのは、オンラインゲーム「ファンタシースターオンライン2(PSO2)」のプレイヤーコミュニティで「ねむねむにゃんこ」が使われた事例です。
ゲームのチャット欄や掲示板で「もう眠いから落ちる、ねむねむにゃんこ〜」といった軽い挨拶が定着し、仲間内でのジョークとして使われるうちに拡散しました。
また、5ちゃんねるのスレッドやAA(アスキーアート)文化とも結びつき、コピペ形式での流布も見られます。
この「コピペ化」は、言葉の意味がどんどん広がっていく典型例であり、本来の文脈を離れて一人歩きする結果となりました。ここまで来ると「誰が最初に言い出したか」を追うのはほぼ不可能になります。
ねむねむにゃんこの元ネタの活用・効果・リアルな声
加賀美(社長)ツイートによる再流行
2023年5月ごろ、にじさんじ所属のVTuber・加賀美ハヤト(ファンから“社長”と呼ばれる)がTwitterで「ねむねむにゃんこ」関連の言葉をツイートしたことで、一気に拡散しました。
ねむねむにゃんこだにゃん🐱
— 加賀美 ハヤト🏢 (@H_KAGAMI2434) May 8, 2023
インフルエンサー的存在の彼が発言することで、元から存在していた表現に再び光が当たり、トレンド入りするほどの注目を集めました。
ここで重要なのは、彼が「元ネタの生みの親」ではなく「再注目させた存在」であるという点です。SNSではこの誤解がよく見られるため、記事で触れる際には区別して説明すると読者に親切です。
三枝明那やVTuber配信でのバリエーション
同じくにじさんじの三枝明那さんが「ねむねむにゃんこだしん」といったバリエーションを使ったことも話題になりました。
VTuber文化の特徴は、配信者同士が互いにネタを取り入れ合い、視聴者もまたコメントで反応しながら二次拡散していく点です。
こうしてオリジナルに近い「ねむねむにゃんこ」に加え、「なのだ」「だにゃん」「だしん」といった語尾変化が派生し、ミームとしての寿命が延びていきました。
特に配信切り抜き動画やファンアートなど、二次創作的な場でも頻繁に見られるようになり、「VTuber発の言葉」と誤認されるほどの定着を見せています。
「と見せかけて」などコピペ的な派生
ネットミームの典型例として「ねむねむにゃんこ、と見せかけて起きてる」などのジョーク形式があり、掲示板やTwitterで流行しました。
この「と見せかけて」構文は、既存のフレーズにちょっとしたオチを加えることで笑いを誘う使い方です。これによって「ねむねむにゃんこ」はただの可愛いフレーズではなく、状況に応じてギャグにも使える柔軟性を獲得しました。
コピペ文化の中では文脈を外れて単体で流れることが多いため、「見たことはあるけど出典が思い出せない」というユーザーが増え、結果的に「元ネタ不明」という印象が強まっています。
SEOや記事で触れる際の注意点
検索ユーザーの多くは「誰が最初に作ったのか」「どの作品が元ネタなのか」を知りたがります。しかし、ねむねむにゃんこについては「単一の公式元ネタは存在しない」という点を明確に伝えることが重要です。
その上で「2019年前後にブログなどで確認できる」「PSO2などのコミュニティで広がった」「加賀美ハヤトや三枝明那といったVTuberが再注目させた」と具体的な事例を提示すると、記事の信頼性が高まります。
E-E-A-Tの観点からも、発言の出典や時系列を整理し、単なる推測ではなく確認できる範囲で事実を提示する姿勢が求められます。
ねむねむにゃんこの元ネタまとめ
総括すると、「ねむねむにゃんこ」は眠さを猫になぞらえた愛らしい表現であり、はっきりとした“公式の元ネタ”は存在しません。
2010年代後半から複数のブログや掲示板で使われ、PSO2プレイヤーやAA・コピペ文化で広まり、2023年以降はVTuberによる使用で再び注目されました。
派生形として「ねむねむにゃんこなのだ」「だにゃん」「だしん」などがあり、「と見せかけて」系のジョークにも活用されています。
記事で扱う際は、「出典が複数あるため確定的ではない」「再流行にはVTuber文化が大きく関与している」という点を添えると、読者の理解が深まりやすいでしょう。