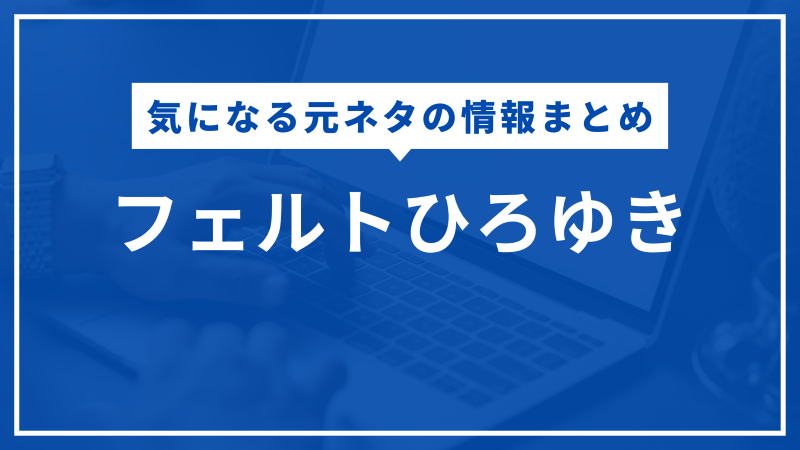フェルトひろゆきの元ネタとは、羊毛フェルトで作られた「ひろゆき氏」にそっくりな人形がSNSを中心に拡散され、さまざまな派生ネタと共に大きな話題を呼んだ現象です。
人形そのものがユニークでかわいいことに加え、「おいら」「竹とんぼ」といったセリフや小物、漫画的な構文表現が合わさり、見る人を笑わせると同時に親しみを感じさせます。
初めて知った人の多くは「元ネタはどこから?」「どうやって作れるの?」「なぜこんなに人気なの?」と疑問に思うでしょう。
本記事では、元ネタの起源や拡散の経緯、羊毛フェルトの作り方、派生表現の面白さまで詳しく解説します。最後まで読むことで、フェルトひろゆきがなぜ注目されるのか、そしてご自身でも制作して楽しめるポイントがわかります。
フェルトひろゆき 元ネタに関する基礎知識と重要ポイント
起源と広がり(概観)
「フェルトひろゆき」は、羊毛フェルトを材料にして作られた小さな人形がSNSに投稿され、そこに独特のセリフや小物が組み合わされて広まったネットミームです。
発端はX(旧Twitter)などで「羊毛フェルトでひろゆき作ってみた」といった軽い投稿でしたが、そのユーモラスな造形と絶妙に付け加えられた台詞が受け、数万リツイート規模で拡散しました。
その後、まとめサイトや動画投稿者が取り上げ、知名度が一気に上がります。さらにはひろゆき氏本人が反応したこともあり、一過性のジョークにとどまらず「ネット文化の一部」として定着しました。
こうしたミームは偶然性が大きいですが、キャラクター性のある人物+手作りアート+ギャグという3つの要素が揃うことで広がりやすくなります。
初出についての注意点
ただし「元ネタの最初の出どころ」は明確に一本化できません。2024年初頭にSNS上で大流行したのは確かですが、一部では2018年ごろの掲示板スレに似た「フェルト人形のひろゆき画像」が投稿されていたとする指摘もあります。
つまり「過去に小規模で存在したネタ」がSNS時代に改めて火が付いたケースと考えられます。ネット文化ではよくあることで、初出をめぐって複数の説が並存するのも自然です。
そのため調べる際には、SNSの拡散時期と掲示板などでの過去ログ、両方を把握しておくと理解が深まります。一次情報をたどりたい場合は、画像投稿の日時や拡散アカウントを丁寧に確認する必要があります。
フェルトひろゆきの元ネタの活用・効果・リアルな声
竹とんぼ
フェルトひろゆきの代表的な派生表現に「オイラの竹とんぼ返してよ」というセリフがあります。小さな人形に竹とんぼを持たせる、あるいは横に置くことで、「ひろゆき人形が子どものように大事にしている物を奪われた」ようなシチュエーションを演出しています。
この“ささやかな小物”を登場させる工夫は、見ている人の想像力をかき立て、単なる人形写真を一気に「物語性のある一コマ漫画」に変えます。
実際の投稿では、竹とんぼの代わりに鉛筆やお菓子が使われるケースもあり、ちょっとしたアイテムを組み合わせることでネタの幅が広がっています。竹とんぼは昭和の懐かしさを呼び起こす玩具でもあるため、世代を問わず笑える共通の題材となっているのです。
作り方(羊毛フェルトの基本)
「自分でもフェルトひろゆきを作ってみたい」と思う人も少なくありません。羊毛フェルトの基本は、羊毛を専用のフェルティングニードル(ギザギザのついた針)で何度も刺し固め、徐々に形を整えていく手法です。
必要な材料は、羊毛(白や肌色を中心に数色)、フェルティングニードル、マット、目玉パーツ(ビーズやプラスチック)などです。
作業工程は①球体を作って頭の形を作る → ②鼻や口を足す → ③体や手足を作り合体 → ④髪型や服を付ける → ⑤最後に目鼻を付ける、という流れになります。
初心者はまずシンプルな動物から始めるのがおすすめですが、フェルトひろゆきは人型なので少し難易度は上がります。それでも顔をデフォルメしてシンプルに作れば十分に雰囲気が出せます。
SNSでは「作ってみた動画」も多く公開されているので、参考にすれば初めてでも挑戦しやすいでしょう。
かわいい(なぜ“かわいい”と言われるか)
フェルトひろゆきが「かわいい」と評される理由は、実在のひろゆき氏のイメージとのギャップにあります。論理的な議論や辛辣な発言で知られる人物が、手作りの丸っこい人形に変換されると、そのアンバランスさが一層面白く、同時に愛嬌を感じさせます。
また、羊毛フェルト特有のふわふわした質感や、少し不揃いな形状は「完璧ではないからこそ愛らしい」という魅力を生みます。
こうした「ちょっと不器用なかわいさ」は、ちいかわやゆるキャラと同じ文脈で受け入れられやすいのです。SNSの反応を見ても「かわいい」「家に置きたい」「なんか守ってあげたくなる」といったコメントが多く、単なるジョーク以上に“癒し”の効果を持っていることがわかります。
「おいら」と台詞の効用
フェルトひろゆきの投稿で繰り返し使われる「おいら」という一人称は、ネット文化の中で“ちょっととぼけたキャラ”を演出する典型的な言葉です。
実際のひろゆき氏も普段「おいら」と言っていますが、この一人称を使わせることで幼い、あるいは不思議ちゃん的なキャラに変換されます。
さらに「おいらの竹とんぼ返して」「ふでばこに隠してほしいんだよ」などの短い台詞は、意外性とリズム感を生み、誰もが真似しやすいキャッチコピー的な効果を持ちます。
この“繰り返しやすさ”こそ、ミームが広がる大きな要因です。単に人形を見せるだけでなく、セリフが添えられることで「人格が宿ったように感じられる」ため、見る人がツッコミを入れやすくなり、拡散が加速していきました。
漫画的表現と構文(ミームの“読み”)
フェルトひろゆきの投稿は、短いセリフと写真だけで成立する「一コマ漫画」に近い形式です。例えば「おいら、ここで寝たいんだよ」「竹とんぼ返して」などのセリフに対し、人形がちょこんと置かれた写真が添えられると、脳内でストーリーが補完されます。
こうした「隙間を埋めさせる構文」は漫画的手法であり、読み手に瞬時の理解と感情移入を促します。
また、文章構造を見ても「おいら(自分の立場)→望み(〜してほしい)→オチ(竹とんぼ返せ)」というリズムが多く、SNSでの拡散に適した“短くキャッチーな構文”になっています。
この構文パターンは模倣されやすく、他の派生ミーム(別キャラクターへの置き換え)にも応用されており、今後も派生が広がる可能性があります。
フェルトひろゆきの元ネタまとめ
フェルトひろゆきの元ネタは、羊毛フェルトで作られた小さな人形と、それに添えられるセリフや小物の組み合わせから生まれたネット文化です。
2018年ごろに小規模に存在していた説もありますが、決定的に広がったのは2024年のSNS拡散でした。人気の理由は「かわいい造形」「漫画的な構文」「小物の工夫」「キャッチーな台詞」の4点にあり、これらが一体となって強力なミームを形成しています。
作り方自体は難しくないため、羊毛フェルト初心者でも挑戦可能ですが、実在の人物を扱うため、遊びとして楽しむ際にはリスペクトを忘れず、ネガティブに扱わないことが大切です。今後も派生ネタが生まれる可能性が高く、ネット文化研究の題材としても興味深い存在といえるでしょう。